運営:有限会社ピィファ・パートナーズ
今月の本
~毎朝5分*2~3冊をご紹介していきます~
毎朝20分ほど読書の時間を作っています。もともとは1冊の本を読み終わるまで別の本を読まないタイプでしたが、そんなことをしていたら、①読みたい本だけを優先する、②積読が増える、③ジャンルが偏る、という事態に陥ってしまいました。そこで子供たちが学校で行っているように「朝読書の時間」というものを設けて、毎日少しずつでも読み進めるようにしたところ、1カ月でだいたい2-3冊は読めることがわかりました。
朝読書のルール
① 1冊5分(切り悪い時は5分以内であれば延長可)
② 1日2-3冊
③ ジャンルはすべて違うものを選ぶ
選書の基準としてはざっくり、自分の専門分野である経済、投資、会計等から1冊、英語・翻訳に関係するものを1冊、その他どの分野でも良いものを1冊、としています。
良かった本、自分の趣味に合わなかった本などいろいろありますが、1カ月で読んだ本をご紹介していこうと思います。
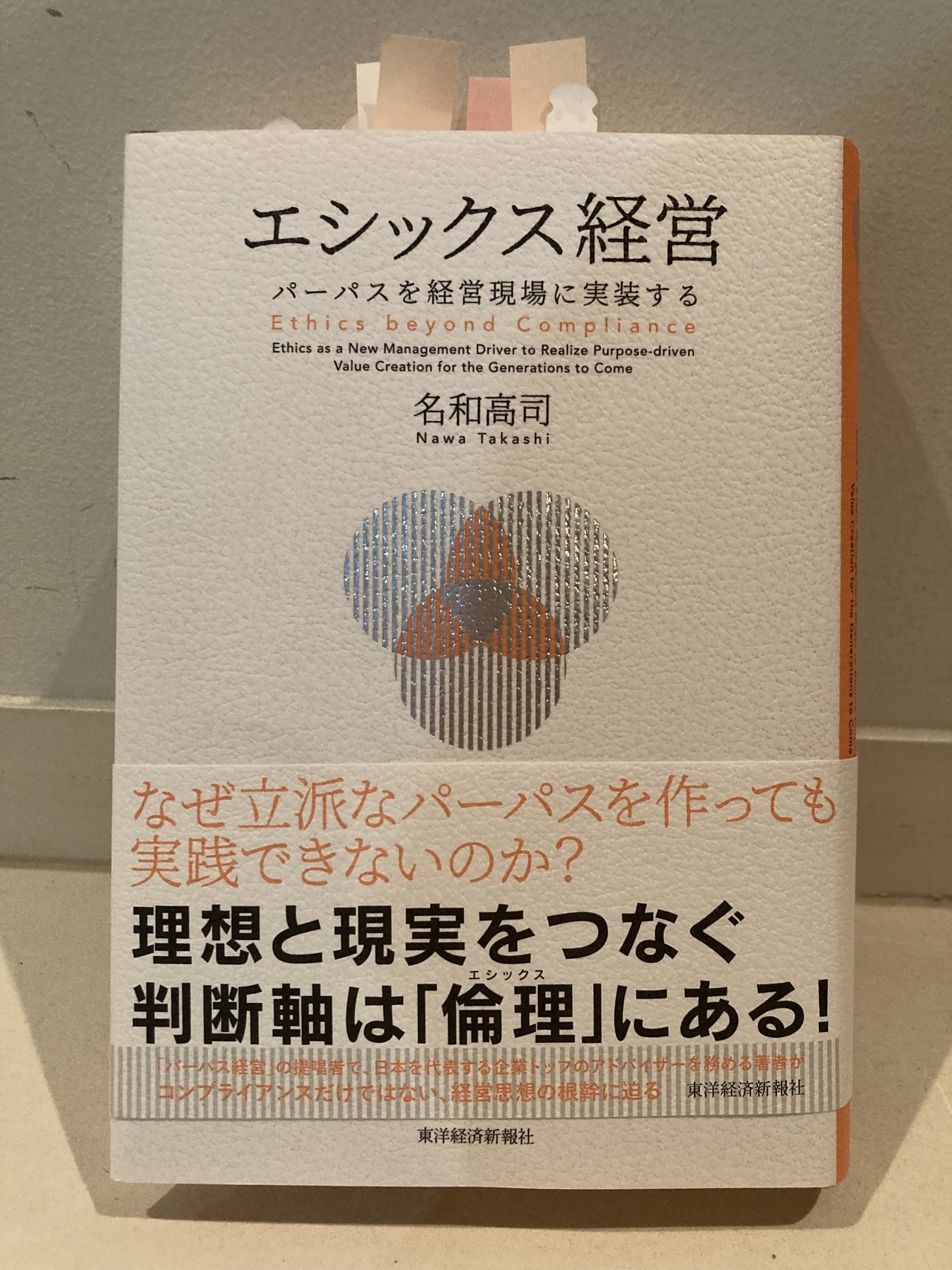
「エシック経営 パーパスを経営現場に実装する」
1. 「エシック経営 パーパスを経営現場に実装する」名和高司 著 東洋経済新報社
猫も杓子も「パーパス」を掲げる昨今、「パーパス」がなぜ機能しないか、という点に焦点を絞った本。パーパスがお題目であるならば、それを実践するには、自分ごととして信念に落とし込まなければならないと説いています。スタートアップが事業を始めるときには、熱意と信念に突き動かされた少数のアントレプレナーが事業拡大に邁進していきます。その事業が軌道に乗って信念の実現に近づくにつれて従業員の人数も増え、もともと共有されていた価値観が薄まっていきます。そうした新しい従業員をも巻き込んで経営を進めていくには、倫理(エシックス)が大事というわけです。そりゃそうだなぁ、と思う一方、その倫理を育む「方法」というのは一筋縄ではいかないのはフジメディア・ホールディングスの迷走を見れば明らか。
少なくとも私の就職活動時代は、フジテレビは入社最難関の会社の一つでした。社員一人一人の資質は日本でもかなり高いほうでしょう。それでも「悪い事・正しくない事」が当たり前のように長年行われていて、だれもそれをオカシイと指摘してこなかった(と少なくともニュースを見る限り外野には思える)企業で、どのように「倫理観」を養うべきだったのでしょうか?社外取締役は、月に1度や2度の取締役会の場で、目の前の課題だけ議論するでなく、その会社の本質的な文化にも切り込んで話をすることができるのでしょうか?会社の「倫理」が崩れていても、問題を提起し、制度や文化を立て直すことができるほど社外取締役は強い存在なのでしょうか?特にオーナー企業では社外取締役がオーナーの一声でいとも簡単に挿げ替えられている実態を見るに、社外取締役という制度にも本質的に問題があるのかもしれません。
エシックスはガバナンスの根幹です。これからフジがどうなっていくのか注目しています。この本はその「方法」を提示するというよりも、倫理がいかに大事か、ということに焦点を絞っており、途中から本当に社会の教科書みたいになっていきます。それが☆の理由。
★★★★☆
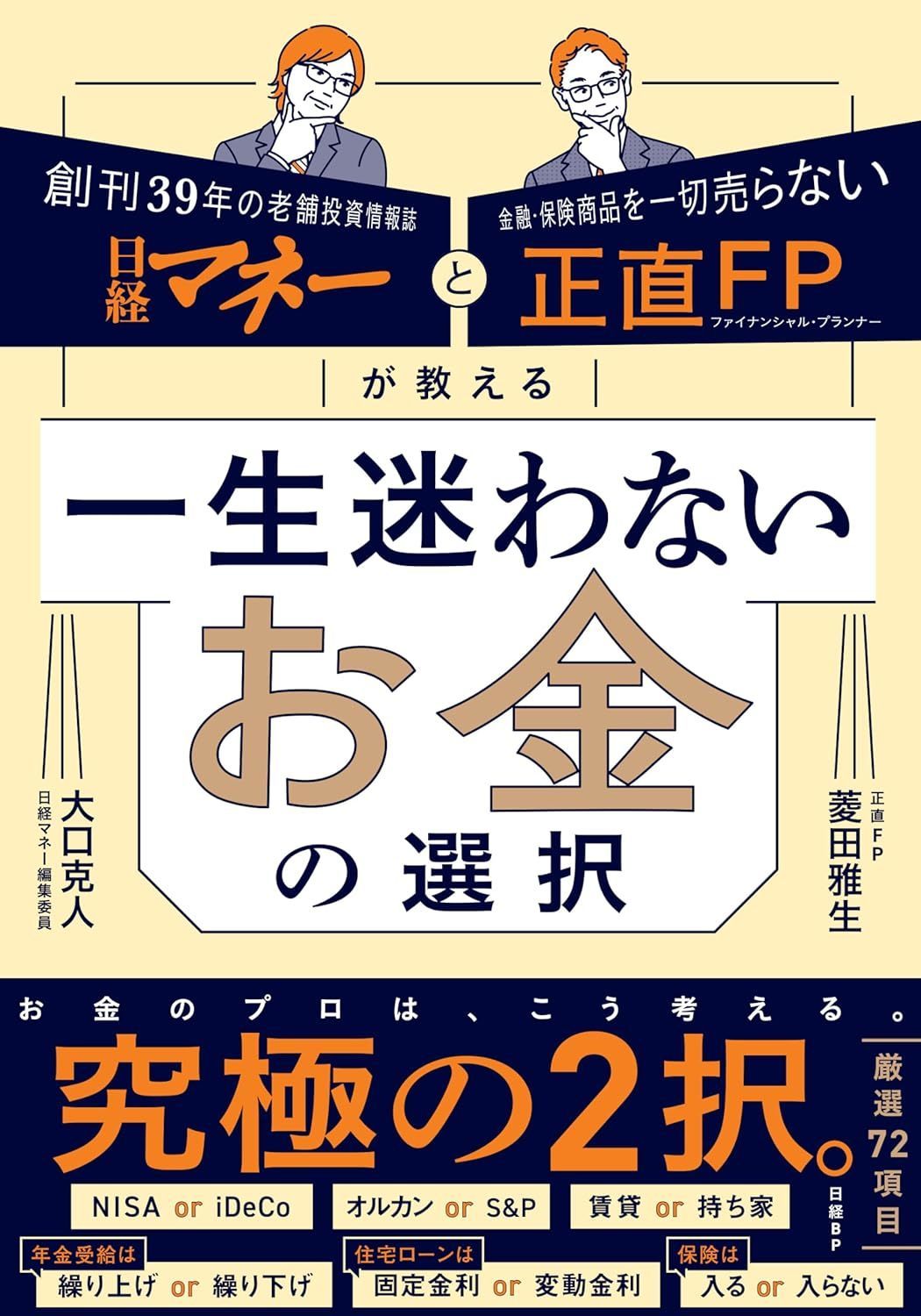
「日経マネーと正直FPが教える一生迷わないお金の選択」
2. 「日経マネーと正直FPが教える一生迷わないお金の選択」菱田雅生 大口克人著 日経BP
J-FLEC講師(その前の証券業協会講師から継続して)を初めて早3年目。今年からは学校だけでなく企業向け講義も増えてきました。その中で特に実感するのは「お金の悩みは幅広く人によってまちまち」ということ。若者向け講義は主に資産運用に焦点を絞って話してほしいと言う依頼が多いのですが、30代~40代では住宅ローン、50代以降では年金と保険、会社経営者からは会社としての退職金の手当ての方法など、さまざまな質問が寄せられます。金融知識もバラバラな中でどのように相手に伝わるのか、ということを試行錯誤している毎日です。
いまやマネー本は百花繚乱です。当たり外れも大きいですが、その中ではこの本は比較的「当たり」本。2023年3月に「経営や会計のことはよくわかりませんが、儲かっている会社を教えてください!」川口宏之 著 ダイヤモンド社という本を紹介しましたが、それと同じように●●とXXどっちがいい?という形で1つの問題に対して回答を出していきます。シンプル過ぎると言えばそうなのですが、入り口としてはいろいろと情報を出すよりも、AとBを比較してそのメリットとデメリットを伝える、というのは有益な伝達方法です。
お金(金融)と法律の知識は人生を守ります。初心者向けなので万民向けではありません(☆)。図書館で借りて返してしまったので写真はアマゾンから拝借しました。
★★★★☆


