運営:有限会社ピィファ・パートナーズ
今月の本
~毎朝5分*2~3冊をご紹介していきます~
毎朝20分ほど読書の時間を作っています。もともとは1冊の本を読み終わるまで別の本を読まないタイプでしたが、そんなことをしていたら、①読みたい本だけを優先する、②積読が増える、③ジャンルが偏る、という事態に陥ってしまいました。そこで子供たちが学校で行っているように「朝読書の時間」というものを設けて、毎日少しずつでも読み進めるようにしたところ、1カ月でだいたい2-3冊は読めることがわかりました。
朝読書のルール
① 1冊5分(切り悪い時は5分以内であれば延長可)
② 1日2-3冊
③ ジャンルはすべて違うものを選ぶ
選書の基準としてはざっくり、自分の専門分野である経済、投資、会計等から1冊、英語・翻訳に関係するものを1冊、その他どの分野でも良いものを1冊、としています。
良かった本、自分の趣味に合わなかった本などいろいろありますが、1カ月で読んだ本をご紹介していこうと思います。
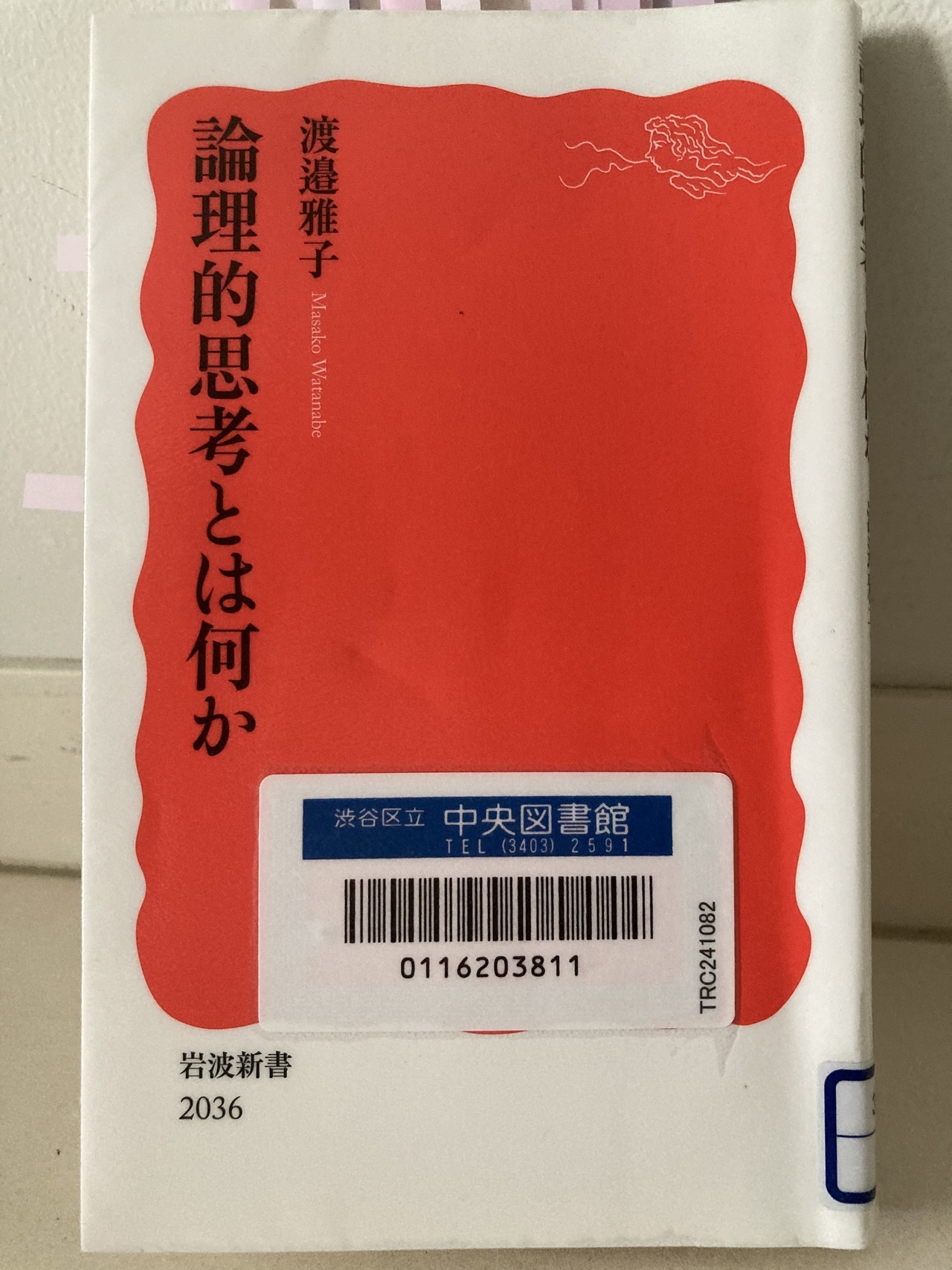
「論理的思考とは何か」
1.「論理的思考とは何か」渡邊雅子著 岩波新書
英文を書くことを生業にしている者は、ロジカルシンキングに基づいて文章を書くことが至上命題とされています。ライティングの講座では必ず、主張ー本論ー結論といった構造を取ること、パラグラフごとにその型を踏襲することを嫌と言うほどやらされます。しかし、この型は米国を中心とした経済効率性の達成を目的としたレトリック(人を説得する技術)に基づいており、アングロサクソン系のライティングが中心の世界でのみ、これが唯一無二のレトリックだと思われているに過ぎないらしいのです(知らなかった!)。
応用言語学者のカプランによれば、読み手が「論理的である」と感じるには統一性と一貫性が必要であり、「読み手」がそう感じるかどうかはその文化や社会の中で馴染んだパターンに落とし込む必要があるそうです。
筆者はそのパターンをアングロサクソン系のエッセイ、フランス系のディセウタシオン、イラン系のエンシャ―、日本系の感想文の4つに分けて説明しています。論理的思考が目的に応じて形を変えて存在するのであれば、この4つにとどまらず、他にも様々なパターンが存在するはずです。しかし、今のアングロサクソン系のエッセイ第一主義に対する疑問に答えるには十分です。
実はこうしたパターン化した文章構造のライティングはAIが得意な分野ではないかと思います。人を説得する技術にAIが秀でているとすれば、生身の人間はどう行動していくべきか、ますます悩ましい。本書は高校生にでもわかるように書いたらしいですが、内容自体はなかなか重厚。図書館で借りて読みましたが買い直そうと思っています。
★★★★★
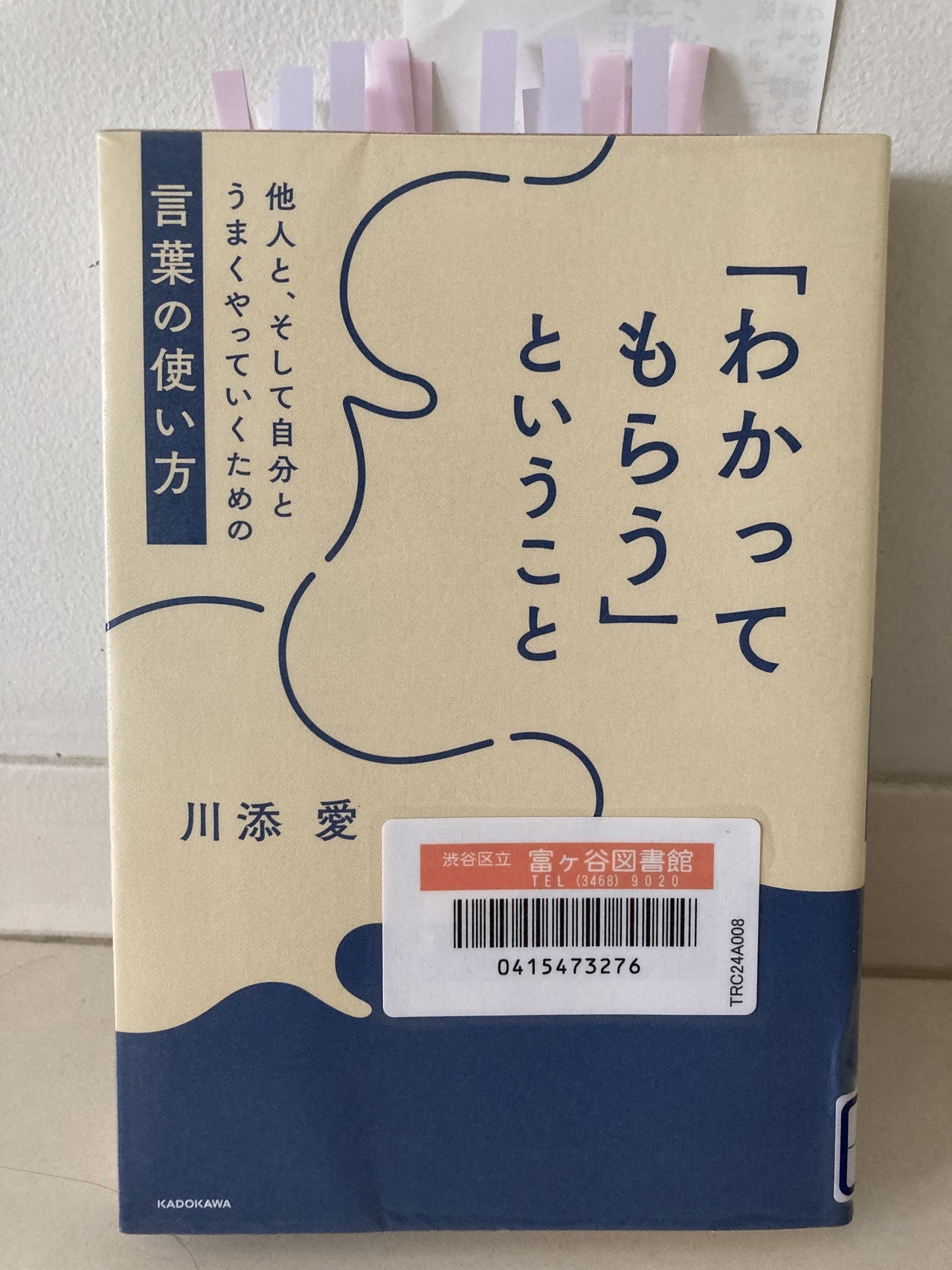
「わかってもらう」ということ
2. 「わかってもらう」ということ 川添愛 著 株式会社KADOKAWA
言語学者、川添愛さんの著書。以前このコラムで取り上げた今井むつみさんの「何回説明してもわからないはなぜおこるのか?」が、わかってもらえないロジックを説明した本だとするならば、こちらはわかってもらうために何をしたらよいかというコツを目的別に書いた指南書と言えるかもしれません。
では、よくある「話を聞いてもらう」ためのハウツー本とどう違うかと言えば、やはり言語学という裏付けのある指南書だけに説得力がある所ではないかと思います。説明において具体例を挙げるとか、実際に手を動かしてもらうことにより理解を深めるというのは一般的な実践方法としてしばしば紹介されています。しかし、それが筆者の体感や経験だけに裏打ちされた方法の場合、読者が腑に落ちないことも結構あります(特に自己啓発本やノウハウ本ではあるあるかと)。その点、「言語学的に~だから~だよ」という説明がついていると納得しやすい。
最終章に「構文を選ぶ」という章があります。その中で「文の途中まで聞いた(/読んだ)人がどう思うか」に気を配るべき、というくだりがありました。「AはBではなく、Cだ」という文の形式で話をすると、聞き手は「AはBだ。でもそうではなく」の「そうではなく」の前までで理解がいったん止まり、「AはBだ」と一旦解釈してしまうわけです。それをその後に「そうではなく」と否定しても、一度理解したものはなかなか白紙には戻せないので、理解が深まらないのだそうです。英日翻訳のときに、Thesis+Body+Conclusionという形式でないと米英の人の理解は中途半端になるので、元の日本語の構造を変えるようにしていますが、これは日本語話者の間でも同じということ?言葉って難しい。
今月読んだ「論理的思考とは何か」で複数の言語におけるロジックの立て方を説明していましたが、そうした基礎知識があるればわかりやすい文章・翻訳に辿り着くのに役立つかもしれません。道は長い。
★★★★★


