運営:有限会社ピィファ・パートナーズ
今月の本
~毎朝5分*2~3冊をご紹介していきます~
毎朝20分ほど読書の時間を作っています。もともとは1冊の本を読み終わるまで別の本を読まないタイプでしたが、そんなことをしていたら、①読みたい本だけを優先する、②積読が増える、③ジャンルが偏る、という事態に陥ってしまいました。そこで子供たちが学校で行っているように「朝読書の時間」というものを設けて、毎日少しずつでも読み進めるようにしたところ、1カ月でだいたい2-3冊は読めることがわかりました。
朝読書のルール
① 1冊5分(切り悪い時は5分以内であれば延長可)
② 1日2-3冊
③ ジャンルはすべて違うものを選ぶ
選書の基準としてはざっくり、自分の専門分野である経済、投資、会計等から1冊、英語・翻訳に関係するものを1冊、その他どの分野でも良いものを1冊、としています。
良かった本、自分の趣味に合わなかった本などいろいろありますが、1カ月で読んだ本をご紹介していこうと思います。
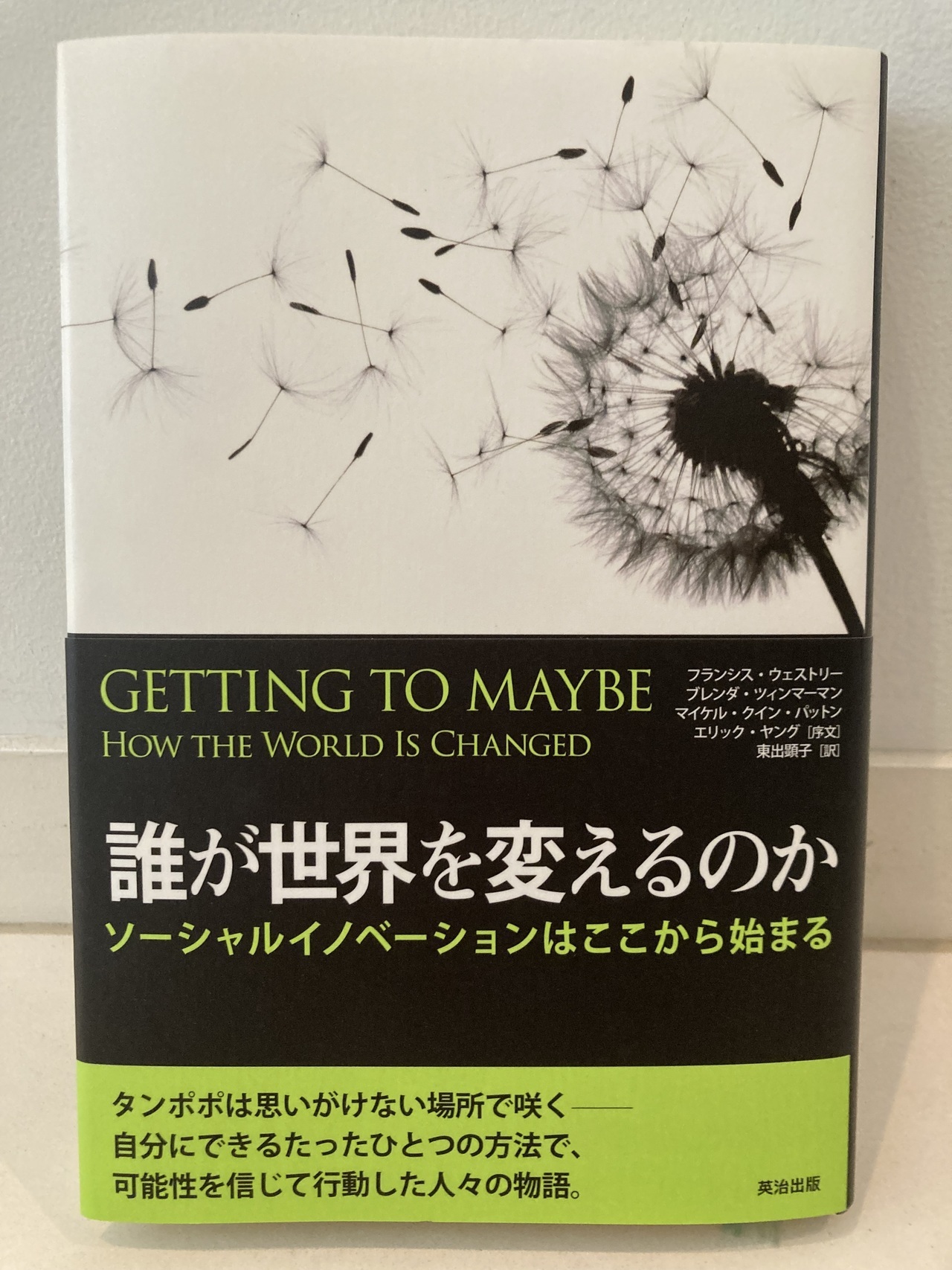
「 誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる」
1. 「誰が世界を変えるのか ソーシャルイノベーションはここから始まる」
フランシス・ウィストリー ブレンダ・ツィンマーマン エリック・ヤング 著
東出顕子 訳 英治出版
2024年は、グッドネイバーズ、UNHCR、ユニセフ、能登地震、認定法人DxP等、気が付けばいろんなところに寄付をした一年でございました(継続寄付も含む)。さまざまな課題や問題を目にするたびに「何とかしたい」と思うけれども、お金を出すことしかしていない自分に恥ずかしさを覚えます。結局贖罪の意識からこうした寄付が増えるのでしょう。
本書はそんな思いを抱えながら、自分にできることで社会を大きく変えた人たちの話。不可能を可能に変える行動には、どんな困難な問題でも解決できるという信念と、フロー(人間がそのときしていることに、完全に浸り、精力的に集中している感覚に特徴づけられ、完全にのめり込んでいて、その過程が活発さにおいて成功しているような活動における、精神的な状態)状態に陥ることが大事だと説いています。
ペンシルベニア大学の心理学教授 アンジェラ・ダックワースもアスリートのような高い目標を達成できる人はフロー状態に陥るケースが多いことを指摘しています。ただフロー状態を経験するには、才能や遺伝ではなく、彼女が言うところのやり抜く力(グリッド)が最も重要だと言います。
本書は社会を変えるムーブメントを起こした人たちのとても勇気づけられる話が満載で、自分も頑張らなきゃと思う反面、結局私がフロー状態になれないのは「グリッド」がないからなのだということを否が応でも気づかされます。この年になってそのことを実感するのはかなり痛い。
でも世の中はきっとまだまだよくなると思わせてくれる、希望に満ちた一冊です。
フローの定義についてはウィキペディア:
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC_(%E5%BF%83%E7%90%86%E5%AD%A6)>
アンジェラダックワースのインタビューはCFAブログにも書いていますのでご参考ください。
https://www.cfasociety.org/japan/society-news-resources/blog/584
★★★★★
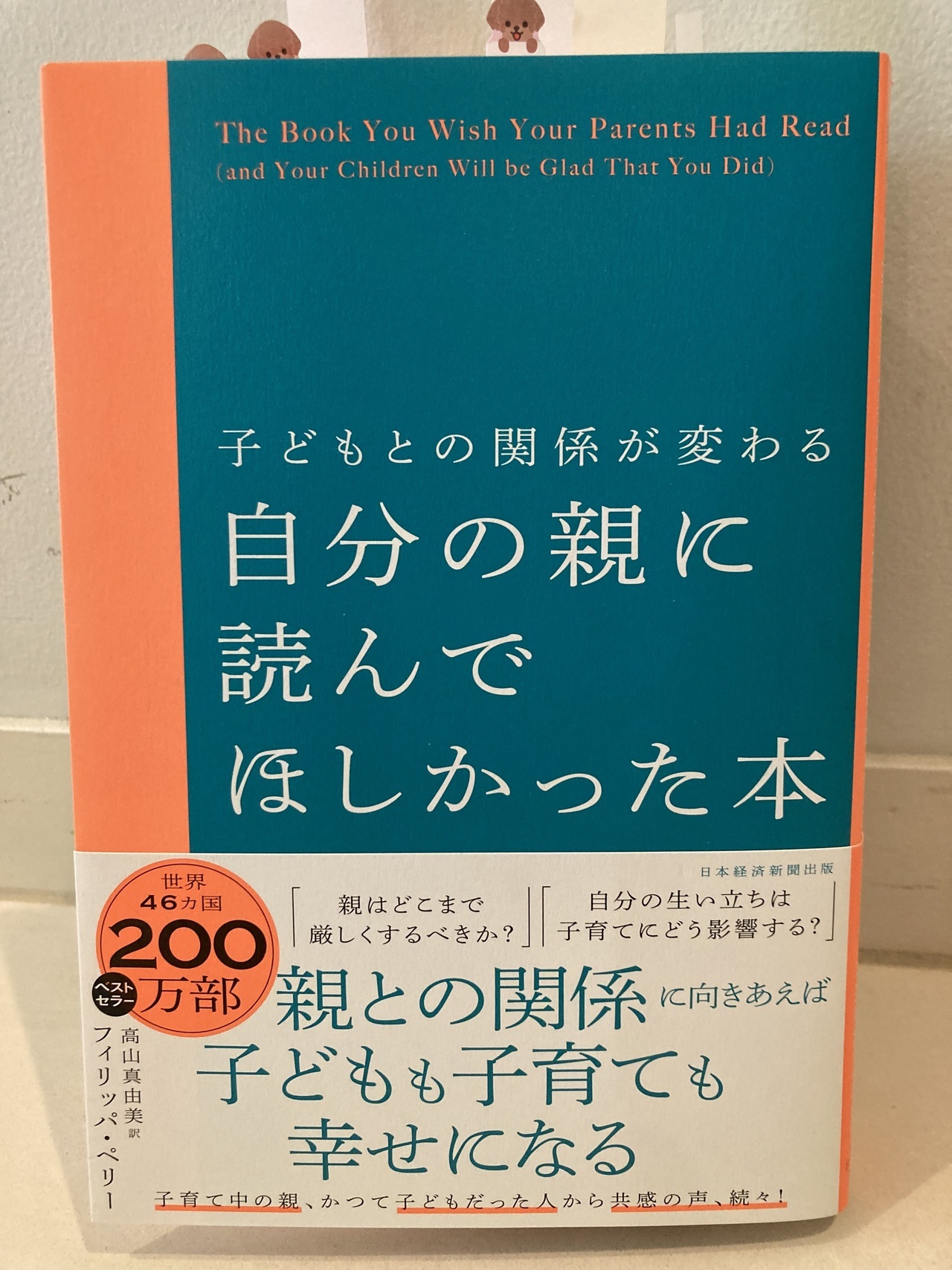
「自分の親に読んでほしかった本」
2. 「自分の親に読んでほしかった本」フィリッパ・ペリー著 高山真由美 訳 日本経済新聞出版
大好きな蔦屋書店に積み上げられていた本。タイトルもキャッチ―ですが装丁もなかなか素敵で思わず手に取ってみました。全体としてはこれまであまたある子育て・家族関連の本の範囲内ではありますが、いくつか面白かった点としては
1.P57 「経験から言って、議論してうまくいくことが多いのは「あなた」を主語にするのではなく、「私」を主語にした場合です。たとえば「スマートフォンをいじっていて、何か言っても答えてもらえないと私は傷つく」のように。」
→私の場合はこの真逆で、「私」を主語にされた会話が立て続けに繰り出されると、自己中心的と感じます。「私はこうして欲しい」「私はこう思う」という主張が続くと、自分のことばっかりで相手のことはどうでも良い人なのかなと。国民性の違いもあるのかもしれませんが、個人によっても随分違うと思いました。
2.P95「不快なことがあったとき、私たちは機嫌を取ってほしいわけではありません。対処するのではなく、共感して欲しいのです。一人ぼっちで嫌な気分に浸らなくて済むように、自分がどう感じているか、誰かに理解してもらいたいのです。」
→これには共感します。こういう場面に遭遇した時、人は解決策やアドバイスを提供しようとしますが、往々にしてうまくいきません。特に男性や年上の人(失礼!)には、ともすれば説教くさくなり、余計関係を悪化させるケースも多いような気がします。私の身近にいる人は話を聞いてほしいだけなのに「嫌な話は聞かせないで。自分も嫌な気分になるから」と言います。愚痴ることもできない。
著者は心理療法士で、タイトルからもある通り子育てに関する内容なのですが、いろいろと対人関係についても当てはまる箇所があります。たまにこういう本を読むと自分や親、子どもについて見直す機会になります。翻訳も癖がなく読みやすいです。内容的にすごく目新しいかといわれればそうでもないところが☆の理由。
★★★★☆


