運営:有限会社ピィファ・パートナーズ
今月の本
~毎朝5分*2~3冊をご紹介していきます~
毎朝20分ほど読書の時間を作っています。もともとは1冊の本を読み終わるまで別の本を読まないタイプでしたが、そんなことをしていたら、①読みたい本だけを優先する、②積読が増える、③ジャンルが偏る、という事態に陥ってしまいました。そこで子供たちが学校で行っているように「朝読書の時間」というものを設けて、毎日少しずつでも読み進めるようにしたところ、1カ月でだいたい2-3冊は読めることがわかりました。
朝読書のルール
① 1冊5分(切り悪い時は5分以内であれば延長可)
② 1日2-3冊
③ ジャンルはすべて違うものを選ぶ
選書の基準としてはざっくり、自分の専門分野である経済、投資、会計等から1冊、英語・翻訳に関係するものを1冊、その他どの分野でも良いものを1冊、としています。
良かった本、自分の趣味に合わなかった本などいろいろありますが、1カ月で読んだ本をご紹介していこうと思います。
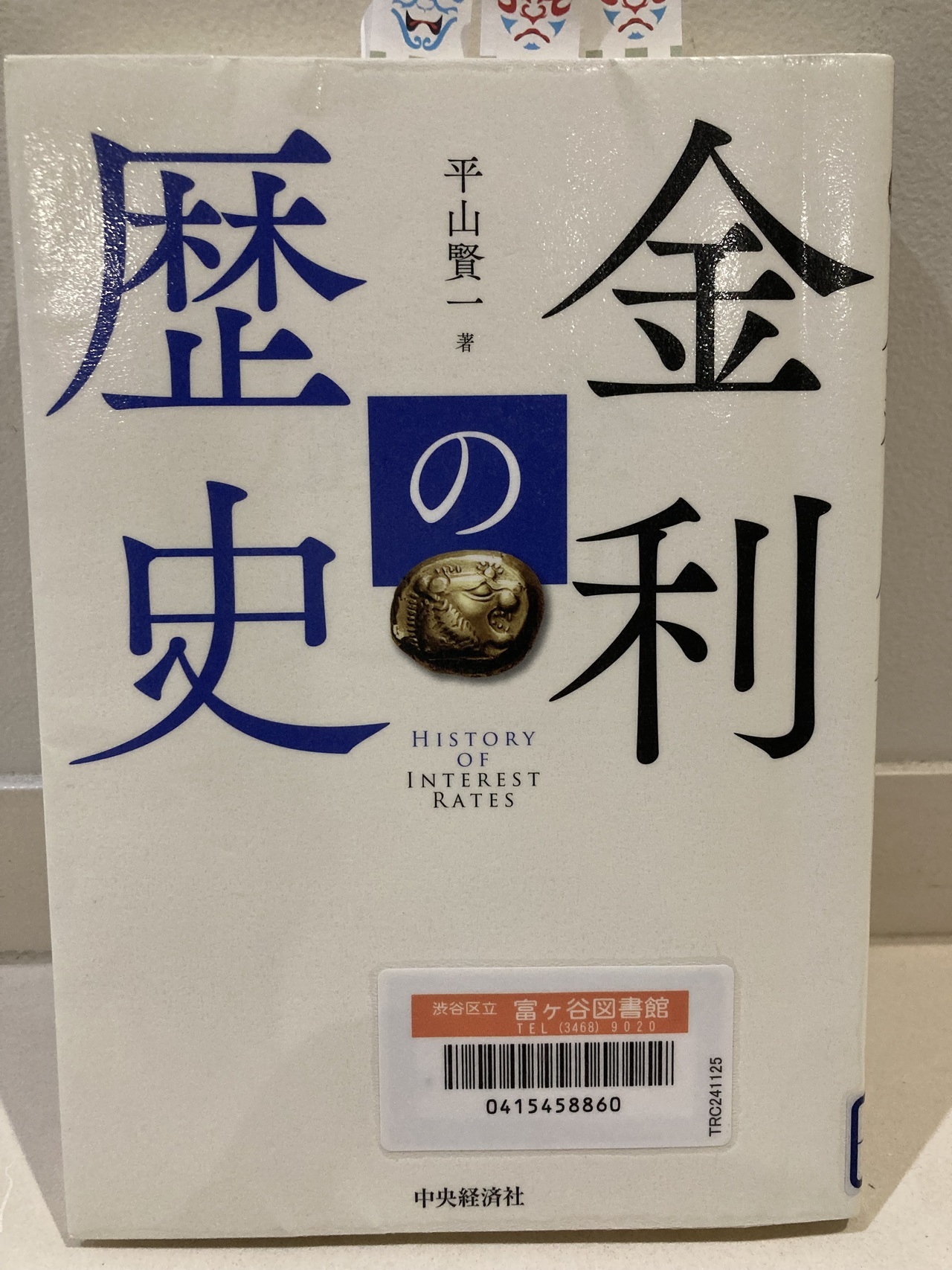
「金利の歴史」
1.「金利の歴史」 平山賢一 著 中央経済社
去る5月29日に行われた日本CFA協会主催「Japan Investment Conference 2025 資産運用立国の実現に向けて」において「3つの壁に直面する個人投資家」というタイトルで本書の著者の平山さんが講演をされました。本書によると、18世紀のオランダの低金利と日本の状況が非常に酷似しているらしい。
私が証券会社に入った1994年当時、すでに金利低下のトレンドにありましたが、国債でも5%くらいの表面利率のものが転がっていました。そこから30年、実にマイナス金利という異次元にまで突入し、現在再び国債、金利市場に注目が集まっています。ちょうど7月21日に行われた参議院選挙で自公の与党連合が過半数割れをして、右派勢力の主張する政策が国債市場を揺るがしかねない状況も考えられます。現時点では懸念するほどではありませんが、今後も金利に対する注目は高まることが予想されます。株式に比べると個人投資家はあまりなじみがない債券ですが、すべては金利が左右するのが金融市場。改めて歴史を紐解いてみるのも良いかもしれません。
とはいえ、この本、ちょっと論文チックなのです。もう少し読み物として堅さが取れると読者も読みやすいのではないかと思います。
★★★☆☆
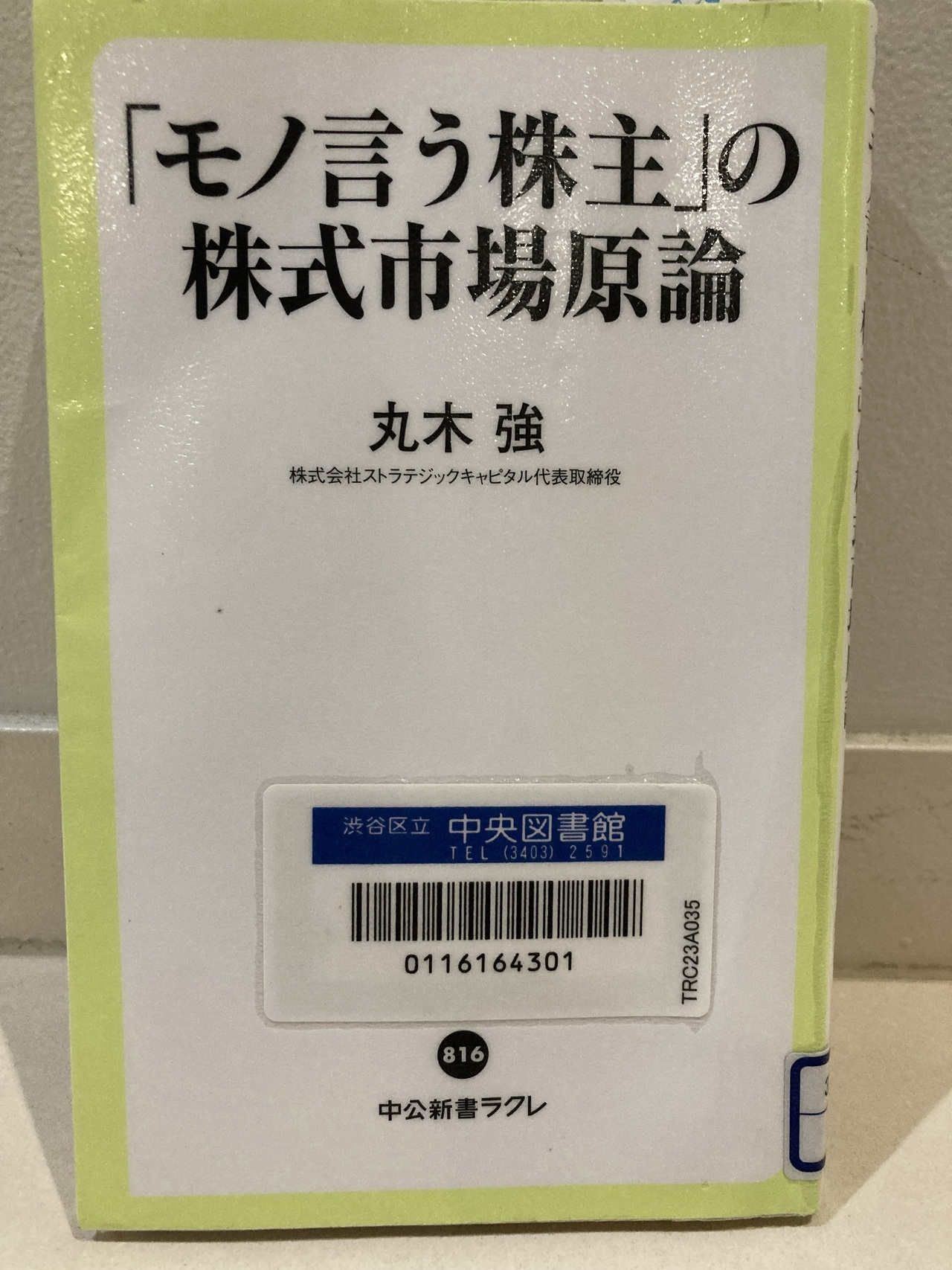
「モノ言う株主」の株式市場原論
2. 「モノ言う株主」の株式市場原論 丸木強 著 中公新書ラクレ
元村上ファンド、現ストラテジックキャピタル代表取締役の丸木さんの著書。資本市場に携わる者としては至極まっとうなファイナンスに基づく意見なのですが、なぜか日本企業の皆様とお話するとかみ合わない。上場企業の経営者のファイナンス知識が少ないような気がします。私も以前、IRコンサルをさせていただいた企業様に、「キャピタルアロケーションの考え方を投資家にお示しした方が良い」と提言したら、社長に猛烈に噛みつかれました。こんなことをする必要はないとはっきり言われました。株主が経営者に付託している最も重要な業務は、正しいキャピタルアロケーションと言っても過言ではありません。それに対する認識が低い企業対投資家の構図はしばらく続くのかもしれません。
むしろ、金融・ファイナンスのプロであるこうしたアクティビストの投資家の意見を「タダ」で借り、ともに企業価値を高めていく方が、特に人材不足の中小企業にとってお得なのではないかと思います。上場会社の数が多すぎるうえ、株主提案など株主の権利が強い日本。エンゲージメントの重要性がますます高まるでしょう。
全体のトーンとしてはやや強めなので、企業経営サイドは少し怯むかもしれませんが、通訳者・翻訳者は投資家のメンタリティを垣間見るうえで参考になると思います。サクッと読める薄さも良き。
★★★★☆


